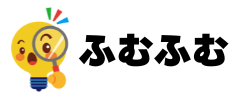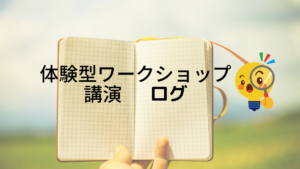勝手な決め付けから生まれる差別。
差別って意外とわたしたちの身近にあるのかも?
あなたも日常生活において、ちょっとした偏見を持ってしまったり、決め付けをしてしまったりしたことはありませんか?
もしくは、他の誰かからそのような扱いを受けて落ち込んだり、傷ついたりした経験はありませんか?
このように、日常生活において誰にでも起こりうる問題はもちろん、人種や病気、障害などを背景として起きる差別によって生じる感情は、その立場になってみて初めてわかるのではないでしょうか。
これらの問題を解決していかなければいけないことを頭ではわかっていても、具体的に何をどうすればいいのかはわかりにくいですよね。一人で考えらることには限界があるし、とても解決できそうにない、と思ってしまいませんか?
実際にその立場になったらどう感じるのか?と体感すること、また、実際に体験している人の話を聴くことによって、あなたの世界がちょっとだけちがって見えるようになると思いませんか?
あなたの「知ろう」という、その一歩で変えられることがたくさんあります。
体験型ワークショップ
講演(LGBTQIA+)
日常生活において誰にでも起こりうる問題を「自分ごと」として体感してもらいます。
ロール・プレイング(注)を通して、日常にあるさまざまな差別や一方的なカテゴライズによって生じる不快感を疑似体験することができます。
ロール・プレイング後にどこに違和感を感じたのか、不快感の原因は何かをシェアし合うことで、差別や偏見についての考えを深めることができます。
(注)ロール・プレイング=役割演技(やくわりえんぎ)とは、現実に起こる場面を想定して、複数の人がそれぞれ役を演じ、疑似体験を通じて、ある事柄が実際に起こったときに適切に対応できるようにする学習方法の一つである。ロール・プレイング(英語: role playing、英: RP)、日本語では略称でロープレなどともいう。
(出典:Wikipedia)
※ロープレ中に差別や偏見などを疑似体験するため、場合によっては体験者本人が気分を害する可能性がございます。本体験型ワークショップは疑似体験を通じて、体験者を取り巻く環境を少しでもよくすることを目的としておりますので、ご了承ください。
主にジェンダーやセクシャリティに関する内容をお話しさせていただきます。
講演内容は、以下のようなものがあります。
・ジェンダーやセクシャリティについての基礎知識
・当事者の体験談、当事者の声
・組織内で取り組めること
・ひとりひとりが、また組織として今日からでもはじめられること
などご相談に応じて構成します。
体験型ワークショップのメリット
参加者同士での意見交換ができる
ワークショップのデメリット
参加人数に限りがある
講演のメリット
参加人数が多くても対応できる
聞きたい話を聞く、ということに集中できる
講演のデメリット
一方通行で終わってしまう
依頼の流れ

ヒアリング

事前アンケート

構成台本の確認

当日

実施後アンケート
参加者の声
(体験型ワークショップ)
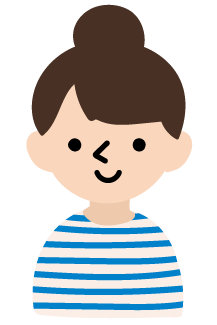
受講者の方々の発言も学びになり、面白かったです。
私にとっては、学びが多く楽しい時間でした。
ワークショップの内容、視点、方法は大変おもしろく考えさせられる内容であると思いました。
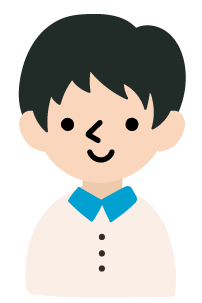
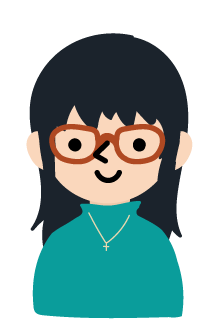

過去の体験型ワークショップ及び、講演のログはこちら
実績一覧(敬称略)
体験型ワークショップ/講演
- 大阪府立学校人権教育研究会 教頭部会(人権研修)
- Aコーン高等学院(生徒対象人権学習)
- 大阪立箕面高等学校(教職員研修、生徒対象人権学習)
- 大阪府立岬高等学校(教職員研修)
- 大阪府立阪南高等学校(教職員研修)
- 大阪府立今宮工科高等学校定時制課程(生徒・教職員合同人権学習)
- 大阪府立学校人権教育研究会 ケーススタディ部会(人権研修)
- 大阪府立守口支援学校(教職員研修)
- 京都市立久我の杜小学校(教職員研修)
- 大阪府立学校人権教育研修B(教職員研修)
- 同志社国際中学校(生徒対象人権学習)
- 同志社国際高等学校(生徒対象人権学習)
- 大阪府立長尾高等学校(教職員研修)
- 桃山学院中学校・高等学校(高等学校生徒対象人権学習)
- 大阪府立阿倍野高等学校(生徒対象人権学習)
- 大阪市立淡路中学校(生徒対象人権学習)
- 大阪府立市岡高等学校
- 大阪府立日根野高等学校(PTA・教職員合同研修)
- 大阪府立中央聴覚支援学校(教職員研修)
- 大阪府立夕陽丘高等学校(教職員研修)
- 大阪府立布施高等学校定時制課程(生徒対象人権学習)
- 大阪市東淀川区民のつどい人権講演会(市民対象人権講演)
- 株式会社フォロアス
- フォトサービスSORAIRO
※以前の活動履歴
- 大阪府立登美丘高等学校(教職員研修)
- 大阪府立堺上高等学校(教職員研修)